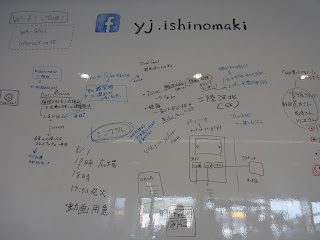.jpg) |
| 世界自然遺産 知床 |
世界遺産条約(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約)が採択されて今年で40周年だそう。登録される時はかなり盛り上がるのに、40周年についてはほとんど報道されていない気がする。わたしがニュースをきちんと見ていないからなのだろうか・・・。
世界遺産条約の基本にあるのは、“人間が自然と相互に作用し合う方法に対する認識が深められ、「自然の保全」と「文化財の保存」は両立されるべきである” という考え方なんだって。
【参考】パンフレット(UNESCO) 世界遺産と持続可能な開発:地域社会の役割
この考え方って大切だと思う。
「世界的に残す価値があるから」 というだけでなく、なぜ、残す必要があるのか、なんのための登録なのかも併せて報道してほしいな。
40周年を迎えた今年のテーマは、「世界遺産と持続可能な開発:地域社会の役割」。
ちなみに、ロンドンオリンピックのテーマは、「持続可能性」。
さらに、今年6月には、10年振りに「国連持続可能な開発会議(リオ+20)」が開催された。
これだけ世界中で“持続可能性 (Sustainability)”という言葉が叫ばれている理由は、現在のわたしたちの暮らしが“持続不可能”だってことなんだな。
持続不可能という言葉の先にあるものはなんだろうか?
恐れずに直接的にいうと、「死」を意味する。
今すぐには死なないけど、近い将来の自分、もしくはそれ以上に自分たちの子孫の命はかなり脅かされていると言っていい。
でも、普段の生活の中では、その切迫感はほとんど感じられない。
じゃあ、どれだけ持続不可能な状態なのか。
人間がどれだけ地球に依存しているかを分かりやすく示す“エコロジカル・フットプリント”という指標がある。日本語に直訳すると、“生態学的足跡”。もう少し分かりやすく言うと、“人間活動が地球環境を踏みつけにした足跡」”。
【参考】エコロジカル・フットプリントで見る、日本がかけている地球への負担(WWF)
要するに、人間一人が暮らすためにどれだけの面積が必要かを示したもので、わたしたち日本人の暮らしには地球2.3個分が必要なんだって。
ちなみに、アメリカは5.1個、インドは0.4個となり、世界平均では1.8個分の地球が必要という計算になるらしい。特に先進国と呼ばれる国が資源を多く利用しているのが分かる。
この状況って、持続可能ではないよね。
世界遺産を増やすのもいい、保護区域を増やすことも必要。
でも、一番必要なのは私たちの生活スタイルを変えることじゃないかな。
地球1個分で暮らせるように、まずは自分の生活スタイルを見直さなければ。
過激な言い方だけども、自分たちの子孫を絶滅に追いやっているという認識を持つべき。
「自分さえ良ければいい」、「今が良ければ後のことは関係ない」なんて、ちょっと悲しいわ。
そんなこと思ってる人も本当は少ないって、まだ信じてる。
今のわたしたちの暮らしは、先進国と途上国の不平等だけでなく、“世代を超えた”不平等を生んでる。
 | |
| 食べ物も国産、地元産を選ぶとか♪ |
そして動いてほしい。世間が動かないくても、自分で変えていけることもあるもの。
それは、窮屈なものではなく、楽しめるものでもある。
考え方次第。視野を広く、楽しめる視点を持って行こう♪
【参考】 診断クイズ わたしの暮らしは、地球何コ分?(NPO法人エコロジカル・フットプリント・ジャパン)